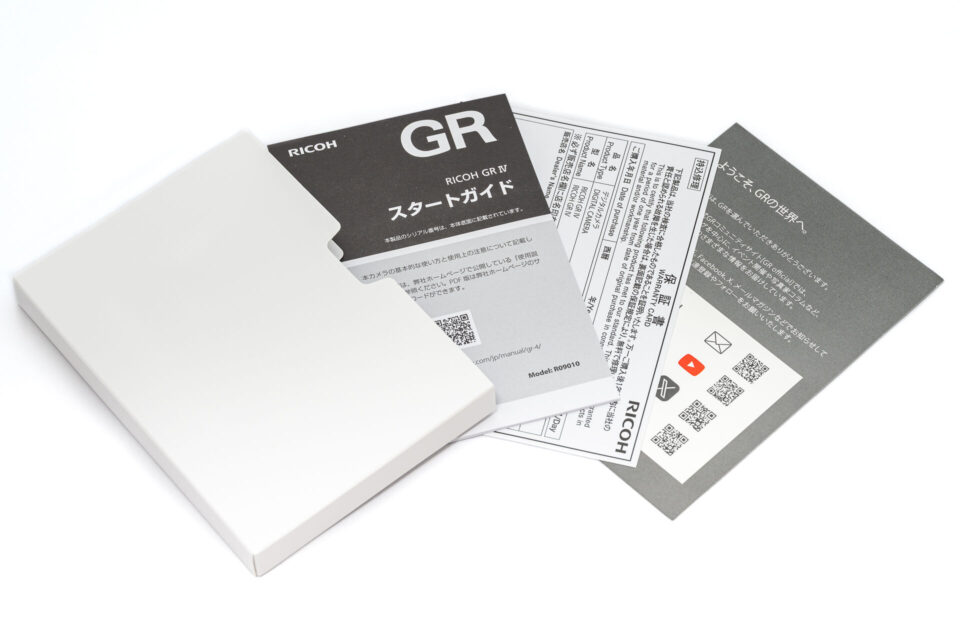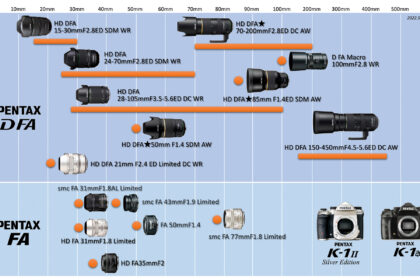RICOHのGRシリーズが6年半ぶりにモデルチェンジした。前モデルのGR IIIはモデル末期で投げ売りされていた…… なんてことはなくて、昨今のインフレやら物不足やらコンパクトデジカメブームとかなんやら、いろいろな要因が重ね合わさったのだと思うが、とにかく長いこと入手難が続き公式ストアでは抽選販売が行われていたほどだ。
そんな状態のまま7月に販売終了したGR IIIに代わり、8月には新型のGR IVが発表され、9月12日に発売開始となった。もちろん手に入れるのは非常に難しい。しばらくは手に入らないのだろうと予約争奪戦に参加する前から半ば諦めていた…… のだが、なぜか公式ストアの抽選に当たってしまった。
さすがにそうなることを見越して、初期ロットはたっぷり作り込んでいたのかもしれない。SNSの観測範囲で見る限り、それほど当選率は低くなさそうに思える。いずれにしても当たってしまったのは何かの縁なわけで、ありがたく与えられた購入権を行使することにした。
開封
リコーイメージングストアでの販売価格は175,320円。いつもらったのか分からないポイントが500ポイントあったので、それを使って支払額は174,820円となった。
箱はかなり小さい。しかもスマートフォンのパッケージのような方式になっていて、なかなか小洒落た感じになっている。
箱の中身は非常にシンプルで、GR IV本体の他に、新型の充電池DB-120とUSB Type-Cケーブル、ハンドストラップだけだ。充電器やACアダプタなどは入っていない。この辺りも今風でとてもよい。
ただし同梱のUSB Type-Cケーブルはイマイチだ。コネクタ部が大きすぎるしケーブルも太すぎ。100W給電とか40Gbps転送に対応しているのか?と突っ込みたくなる(実際そうなのかもしれない)。高速データ転送も大電力充電も必要ないGR IVにこんな野暮なケーブルを組み合わせるのはどうかと思う。
紙類についてもペラペラのスタートガイドの他は、保証書とGRのSNSアカウントの紹介カードのみ。詳しい説明書はWEBからダウンロード出来るようになっていて、そのQRコードがスタートガイドの表紙についている。この点もとてもよい。
あとはGRのステッカーでもおまけで入れておいてくれたら良いのに(要求が多い客)。
本体はこんな感じ。これだけ見ていると今までのGR IIIと何が違うのかよく分からない。
電池を入れて電源を入れるとこうなる。見た目はやっぱり差が分かりにくいが、実は電源を入れた瞬間に差を実感することになる。
GR IIIでも十分に速いと思っていた起動が、体感で分かるくらいにもっと速くなっているのだ。沈胴式のレンズを繰り出す工程を含めてこのスピードを実現しているというのは本当にすごいと思う。
ちなみにGR IVではCMOSセンサも画像処理エンジンも新しくなっただけでなく、レンズも新設計となっているらしい。見た目と違って中身はほとんど別物になっているのだ。
背面のボタン類を良く見るとGR IIIとの差が見つかる。GR IIまであった+/-レバーが復活し、十字キー周囲のホイールがなくなっている。これらにともなって微妙に凸凹の造形も変わっている。ADJレバー&ボタンはADJダイヤル&ボタンとなっている。
ちなみにここで書いておくと、個人的にはGR IIIのADJレバーはそれほど嫌いではなかった。GR IIIのフニャッとした押し心地に対し、GR IVはADJボタンとしてのクリック感が少し固すぎるように思える。
上部の操作系はこんな感じでほぼ変わりがないが、モードダイヤルにSn(スナップ)モードが追加されていたりする。
あと、機能的に重要なところではPモードがプログラムオートExに進化している。これはPENTAXでいうところのハイパープログラムと全く同じ機能だ。そのハイパー操作系で重要となるグリーンボタンはどこにあるかと言えば、なんとモードダイヤルのロックボタンがグリーンボタンとして機能している。なるほど、そう来たか!
さらに重要な変更点は電池とメディアだ。特に電池はGR III/IIIxで使われていたDB-110から変更され、新型のDB-120という角形の電池になった。容量は1セルの1800mAh/6.9Whと大容量化した。そのおかげもあってGR IVの電池寿命はCIPA基準で250枚と、GR III/IIIxの200枚から増えている。
記録メディアはとうとうmicroSDカード(UHS-I)になってしまった。まぁ、この辺は仕方がない。スペース効率を考えたらこれしか手がないのだろう。その代わりと言ってはなんだが、内蔵メモリーが大幅に増やされて約53GBもある(GR III/IIIxは約2GB)。読み出しをどうするか次第だが、運用としては内蔵メモリーだけで済ませるということも十分可能だと思う。
もう一つ重要な変更点があって、それはボディの厚みだ。GR IV単体で見ているとあまり分からないというか、うっすらと違和感を抱く程度だと思うのだが、GR III/IIIxと並べたり持ち比べると明らかにボディが薄くなっていることが分かる。
GR IIIでも十分に小型だったし、大きさやボディの厚みについて何か意見が多く寄せられていたとは思えないのだが、とにもかくにもボディの薄型化にかなり心血が注がれているようだ。電池の変更、microSDカード化、そしてレンズの再設計などもすべて絡んでいることなのだろう。
重量は262gでGR IIIより5gほど重たくなっているが、そのほとんどは電池による。だが、体積が小さくなったせいか手にした時に重量感が増したように思える。高級感という意味では良いことなのだが、軽快さはあまりない。
そんなこんなでバッテリーの充電と設定やボタン類のカスタマイズを(暫定的に)終えたところで、いよいよ撮りに出かけてみようではないか。
……とその前に、とりあえず液晶保護ガラスとmicroSDカードを入手した。
液晶保護ガラス(or フィルム)は有名どころにした方が無難だが、まだ各社製品が出そろっていないようなので、Amazonで無銘の2枚入りガラスにしてみた。変なプラスチックケースに入ってきたが、ゴミ取りのシールやアルコールクロスが入ってきたりするところは、どちらかというとスマホの保護ガラスの流れを汲んでいる製品のようだ。ちょっとサイズが大きい気がするが見た目と触り心地は悪くなさそうなのでこのまま使ってみようと思う。 microSDカードは何枚か手持ちのものがあるのだが、やはり新しいカメラには新しいカードで心機一転したいということで、Nextorageの128GBを1枚買ってみた。スピードクラス10、U3、A2のもの。似たようなスペックでいくつも製品はあるが、最近はNextorageがお気に入りなのでその中で一番安いやつを選んでみた。試しに撮影
さっそく撮影に出かけてみた。とはいえまだ病み上がりだし気温もまだまだ高く、天候も不安定だったので近所を散歩した程度だ。
夕暮れ空。イメージコントロールはGR IVで新たに追加された「シネマ調(Yellow)」を使って黄色味を強調している。と言うか、Lightroom (Classic) / Camera Raw はすでにGR IVのカメラプロファイルをサポートしていて、すべてのイメージコントロールを再現しつつDNGから現像することができる。
最近道端によく見かけるランタナ。野生化した外来種らしく、その生命力の強さがうかがえる。黄色味がかかったローキー調でこってり色が乗った感じはやはり「シネマ調(Yellow)」による。
GTエンブレム。一瞬白黒に見えるかもしれないが白黒ではない。これはもう一つ追加された「シネマ調(Green)」を使った。カメラ内で粒状感を追加することもできるのだが、このカットはLrで後から加えている。
うち捨てられた自転車。これも「シネマ調(Green)」で撮った(現像した)。
うち捨てられたカラーコーン。
これもまた「シネマ調(Green)」だ。比較的彩度が低くシャドウが締まっていて色はその名の通りグリーンに傾いている。クールな感じに仕上げると言えばブルーを被せると思い込んでいたが、最近はグリーンの扱いが鍵だと気づきはじめていたところで、この色味はけっこう嵌まるかも?と感じている。
これは今までのGR III/IIIxにも入っていて最近のお気に入りだった「ネガフィルム調」で撮った。彩度が低いところは「シネマ調」と似ているが、全体的にコントラストが低くて淡い。これもやっぱり良い。常用はやはりこっちか。
ハードモノトーンで葛西橋通り。取り壊されて絶滅しつつある歩道橋の上からの眺め。GRを使う大写真家の作品を真似たくなって、モノクロで撮りがちになるのもGRあるあると言えるだろうか。
秋の気配がほんの少しだけ出てきた空。もちろん普通に「標準」のイメージコントロールで撮れば普通にきれいに写る。むしろキリッと鮮やかで爽やかな写真をGRで撮ってみたい。
近接撮影にも相変わらず強い。とはいえ28mm相当なのでパースや背景の処理とか色々考えないといけない。と言いつつ、そればかり気にしてるとこういう変なアングルの写真になってしまう。ケーキとコーヒーは美味しかったからまぁいいか。
高感度はまだよく分からない。このカットはISO3200なので今の時代それほど高感度というわけでもないが、思ったよりはクラシックな感じというか、わりとザラッとしている面があるように思える。ただ、これがISO6400とか超えてもそんなに変わらない感じがしている。
いずれにしてもノイズの粒の出方はそんなに嫌な感じではないし、今やむしろ後からわざわざ粒状を乗せたりもすることがあるわけで、ゴリゴリに塗りつぶされてノッペリして妙にS/N感の良い写真よりは「味わいがある」と言っておくべきだろうか。
ファーストインプレッションまとめ
ということで、手にしてまだ数日の段階、総撮影枚数もまだ100カット程度に過ぎないが、現時点でのファーストインプレッションをまとめておこうと思う。文章にするとダラダラになりそうなので、箇条書きにしておく。
まずは良いところ。
- GR IIIの良さを何一つ失わずそのまま引き継いでいるところ
- なのに少し薄くなっているところ
- 起動はじめ動作が速くなっているところ
- 手ぶれ補正が強化されているところ
- 内蔵ストレージが53GBもあるところ
- 新型電池の採用により電池寿命が延びたこと
- Bluetooth/Wi-Fiの接続性がようやく「普通」レベルになったこと
- ハイパープログラム(敢えてこう表現する)を搭載したこと
- ワイドコンバーターGW-4が流用できること
こんな感じだろうか。だいたいすでによく言われていることばかりだと思う。
次に、この短い使用期間で「どうかな?」と感じたところと「こうだったら良かったのに」と思ったところ。
- ボディが熱くなるところ(GR III/IIIxより熱いと感じる)
- ADJボタン押し込みが固すぎるところ
- 動画がFHDまでなところ
いまのところこのくらいかな?と思う(価格や供給のことは敢えて言わない)。使い込んでいくと良いところも悪いところも感じ方は変わっていくことだろう。
動画について少し触れておくと、GRには動画は不要だしどうでも良い、と考えているユーザーがほとんどであることを承知の上で、それでも今どき4K/30pくらいは普通に撮らせて欲しいと思う。もちろん熱処理とかいろいいろあって「GRとしては敢えてコストも時間もかけるところではない」と言われたら「そうですね」と同意せざるを得ない。
しかしGR的な「スナップ」の延長線上にショート動画の世界はあるんじゃないのかな?という気が個人的にはしていて、頑なに静止画機としてのGRのコンセプトを守り続けるのも良いのだが、新しい提案もちょっとずつ必要なんじゃないかな?と、誠に僭越ながらそう思うのだ。(※ 個人のごく軽いお気持ちです)